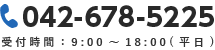こんにちは。八王子市の伊橋行政書士です。
きょうは、ご質問にQ&Aでお答えしていきましょう!
1. 視聴者の質問と問題提起
「高齢の親が認知症になったら、財産の管理はどうすればいいのか?」
みなさん、こんな不安を感じたことはありませんか?例えば、親名義の不動産を売りたいけど、本人が認知症で判断能力がなく、契約ができない。銀行の口座から生活費を引き出すのも難しい。そんな時、どのような手段があるのか知りたいと思いませんか?
2. 共感部分
本当に困りますよね…。親が元気なうちはいいけれど、突然の病気や認知症などで判断能力が低下すると、財産の管理や生活費の支払いに困る方が非常に多いです。成年後見制度もありますが、手続きが煩雑で費用もかかりますし、家族が自由に財産を管理できるとは限りません。そんな時に役立つのが「民事信託(家族信託)」なんです!
3. 法律上の解決策の提示
では、民事信託(家族信託)がどのように高齢者サポートに使えるのか、具体的に解説していきます!
Q1: 民事信託(家族信託)って何ですか?
民事信託とは、自分の財産を信頼できる家族や親族(受託者)に管理や運用を任せる仕組みのことです。親が元気なうちに、家族と信託契約を結んでおくことで、認知症などで判断能力が低下した場合でも、受託者がスムーズに財産管理を引き継げるんです。
Q2: 実際にどのように活用できますか?
例えば、親名義の不動産を家族信託の対象にしておけば、受託者が売却や賃貸契約をスムーズに行えます。また、親の預貯金を信託財産にしておくことで、必要な生活費を管理しながら使うことも可能です。

Q3: 契約を結ぶときの注意点はありますか?
信託契約を結ぶ際には、親がまだ元気で判断能力があることが大前提です。また、契約書の内容が法律に基づいていないと無効になる場合もあるので、専門家のサポートを受けることが重要です。
4. 関連法律とポイント解説
Q1: 民事信託は成年後見制度とはどう違うんですか?
民事信託は事前に対策を講じる仕組みで、財産管理を柔軟に行えるのが特徴です。一方、成年後見制度は判断能力を失ってから裁判所を通じて後見人を選任する仕組みで、家族が自由に財産を管理するのは難しい場合があります。
Q2: 信託契約に必要な書類や手続きは?
信託契約書を作成し、公正証書として残すのが一般的です。また、不動産を信託する場合は、登記簿の名義変更も必要になります。
Q3: 税金の問題はどうなりますか?
信託財産の移転には贈与税がかかる場合もあるため、税理士などとも連携して事前に計画を立てるのが重要です。
5. 専門家活用の勧め
ここまで、民事信託の基本と活用法についてお話ししましたが、実際に契約書を作成したり、税金の問題をクリアしたりするには、法律や税務の専門的な知識が必要です。
「家族信託を考えてみたい」「親の財産管理について相談したい」と思ったら、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。私たち行政書士は、信託契約の作成やアドバイスを通じて、みなさんの安心した暮らしをサポートします!
最後に
最後までご覧いただきありがとうございます!民事信託(家族信託)は、親の将来を守る素晴らしい仕組みです。高齢者の安心を支えるために、ぜひ一度ご検討くださいね!次回も役立つ情報をお届けします。